第59回離婚弁護士コラム 【協議離婚に対応】離婚手続きの流れと準備のポイント|成立までに必要なステップとは?
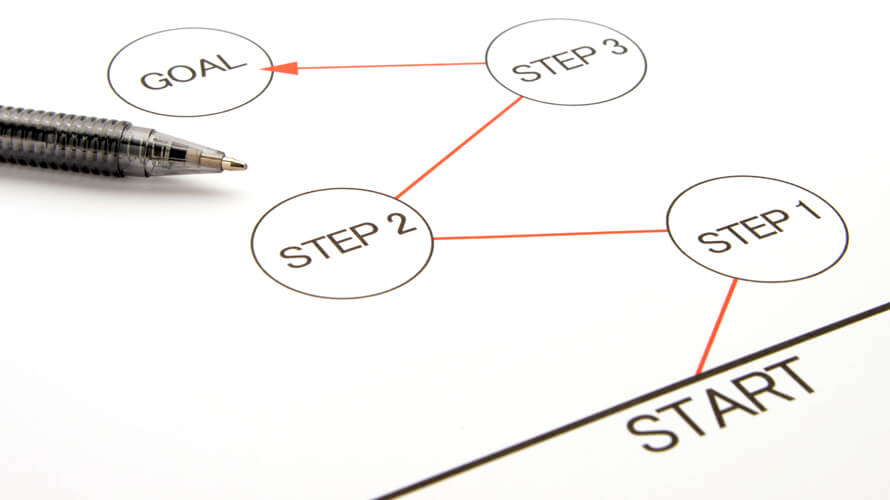
離婚を検討し始めたとき、「何から手をつければいいのか」「どんな書類や準備が必要なのか」と不安に感じる方は少なくありません。
特に、子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流などの取り決めも必要になり、手続きはより慎重に進める必要があります。
本記事では、主に協議離婚を前提として、離婚成立までの流れをステップごとに解説。加えて、子どもがいる家庭で特に注意すべきポイントも紹介します。
トラブルを防ぎ、スムーズに新生活をスタートするための知識を、この記事でしっかりと押さえておきましょう。
離婚手続きの基本とは?
離婚手続きとは、法律上の婚姻関係を正式に解消するために対応すべき一連の手続きのことを指します。ただ単に「別々に暮らす」といった事実だけでは法的な離婚とはみなされません。必須条件の手続きを経ることで、はじめて法的に離婚が成立します。
離婚手続きの必要性
離婚届を提出し、役所に受理されなければ、法律上は夫婦のままとなります。戸籍上の婚姻関係も継続されるため、たとえ別々に暮らしていても「法律上の配偶者」として扱われてしまいます。これにより、再婚ができなかったり、相続や保険の手続きで不都合が生じたりする可能性があります。
離婚手続きの種類
日本の法律では、離婚の方法として主に4つの種類が用意されています。どの手続きを選ぶかは、夫婦間の合意の有無や争点の内容によって異なります。各手続きの特徴を理解することで、自分たちに合った進め方を選ぶことができます。
1. 協議離婚
もっとも一般的な方法で、夫婦の話し合いによって合意が成立すれば、離婚届を役所に提出するだけで完了します。日本で成立する離婚の約9割がこの方法。親権や養育費、財産分与などの取り決めは書面に残しておくと、後のトラブルを防げます。
2. 調停離婚
夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員を交えた話し合いを通じて合意を目指します。これを「家庭裁判所の場で行う話し合いによる離婚」と考えるとわかりやすいでしょう。調停が成立すると、その内容に基づいて離婚が成立します。
3. 審判離婚
調停が成立しない場合でも、一定の条件を満たせば、家庭裁判所が職権で離婚を命じることがあります。これが審判離婚です。ただし、当事者のどちらかが異議を申し立てれば無効になるため、実際に利用されることは非常に珍しいです。
4. 裁判離婚
調停でも合意ができない場合は、裁判によって離婚の可否を争う「裁判離婚」へと進みます。裁判で離婚が認められるには、民法で定められた「法定離婚事由」に該当する必要があります。代表的なものには、不貞行為や悪意の遺棄、3年以上の生死不明などがあり、これに該当しない場合は離婚が認められにくく、ハードルが高くなります。
証拠の提出や証人尋問など、専門的な対応が求められるため、弁護士など法律の専門家に相談することが重要です。
協議離婚の手続きの流れ|離婚成立までのステップ
日本で最も一般的で、主に夫婦間の合意によって進める協議離婚について、手続きの流れを解説します。離婚を成立させるには、「話し合いの合意」から「届出の提出」まで、いくつかの重要なステップを踏まないといけません。感情的な混乱の中でも、冷静に手続きを進めることで、離婚後の生活への不安やトラブルを最小限に抑えましょう。
離婚条件を整理・合意する
離婚を成立させるためには、単に「別れたい」という意思だけでなく、具体的な離婚条件についての合意が欠かせません。後々のトラブルを防ぐためにも、話し合いの段階で必要事項を整理し、当事者間でしっかり合意しておくことが望ましいです。
整理すべき主な離婚条件
1. 親権者の決定
2. 養育費の取り決め
3. 面会交流のルール
4. 財産分与
5. 慰謝料の有無
書面化しておくことの重要性
口約束だけでは、離婚後に「言った・言わない」の争いが発生する可能性があります。合意内容はできるだけ書面にまとめ、特に養育費や慰謝料などの支払いについては、公証役場で「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておくと、支払いが滞った場合に裁判を経ずに差し押さえ等の手続きが可能になり、安心です。
離婚手続きの最終ステップ|離婚届の提出方法
離婚の合意が整ったら、次におこなうのが離婚届の提出です。これは、法的に婚姻関係を解消するための最終ステップとなります。書類の記入や提出先、必要書類などに不備があると受理されない可能性もあるため、事前の準備が大切です。
離婚届の入手と記入
離婚届は、全国の市区町村役場でもらえます。また、多くの自治体では公式サイトからダウンロードも可能です。
記入項目には、以下のような情報が含まれます。
・夫と妻の氏名・住所・本籍地
・離婚の種別(協議離婚・調停離婚など)
・未成年の子どもがいる場合は親権者の記載
・証人2名の署名(協議離婚の場合のみ)
記載内容に不備があると、提出しても受理されないことがあるため、慎重に確認しましょう。
提出先と持ち物
離婚届は、本籍地・所在地・所在地のある市区町村役場のいずれかに提出できます。本人が直接窓口に出向くほか、郵送での対応も可能です。必要な持ち物には以下のようなものがあります。
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(自治体によっては不要の場合も)
・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
離婚が成立するタイミング
離婚届が役所に受理された日が、法的な離婚成立日となります(※住民票や戸籍に反映されるタイミングは別日になる場合もあります)。提出しただけではなく、「受理される」ことが重要なポイントです。役所からの確認連絡が入ることもあるため、日中に連絡が取れる電話番号を記載しておきましょう。
子どもがいる場合の離婚手続きのポイント
未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合、子どもの生活や権利を守るための取り決めが必要不可欠です。離婚後も親としての責任は続くため、感情的な対立にならないよう、子どもの将来を第一に考えた話し合いが求められます。以下では、子どもがいる場合に押さえておくべき手続き上の重要なポイントをお伝えします。
親権者の決定
協議離婚の場合、離婚届には必ず親権者を記載しなければなりません。どちらか一方が親権を持つことになります。親権をめぐる争いは長引く傾向が高く、感情的になりがちですが、子どもの福祉を最優先に冷静な判断が必要です。
養育費の取り決め
親権を持たない側も、子どもを育てるための費用(養育費)を分担する義務があります。養育費の金額や支払期間、支払方法などを明確に話し合い、できれば「公正証書」などの形で書面に残しておくことが望まれます。将来の未払いトラブルを防ぐためにも重要な手続きです。
面会交流のルール
面会交流は、離れて暮らす親のためだけでなく、子どもの健全な成長にとっても重要な権利とされています。面会の頻度や方法(対面・電話・オンラインなど)を取り決めることで、子どもの精神的な安定や親子関係の維持につながります。両親の関係性が悪くても、子どもにとって何が最善かを基準に考えることが大切です。
おわりに―離婚と手続きの基本を押さえて、後悔のない選択を
離婚の手続きは複雑に感じるかもしれませんが、正確な知識を身につけ、段階的に準備することで、落ち着いて進められます。
とくにお子さんがいる場合は、子どもの将来を見据えた判断が求められます。不安な点があれば、弁護士など専門家のサポートを活用しながら、一歩ずつ前進していきましょう。
当事務所では、離婚に関する無料相談を実施しております。多くの離婚案件に携わってきた専門の弁護士が、皆様の離婚後の新しい生活を応援するべく親身になって離婚に際しての条件面や内容面をアドバイスさせて頂きます。親権、子の引き渡し、離婚問題でお悩み・不安のある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。