第65回離婚弁護士コラム 離婚後に財産分与を請求するには?期限・方法・注意点まとめ
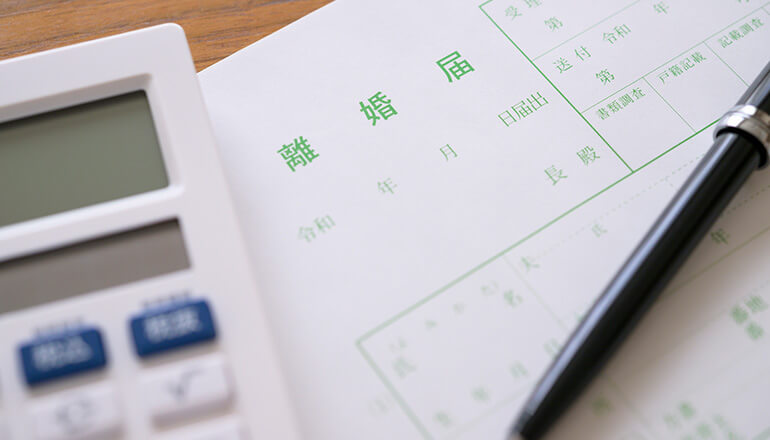
離婚を考えるとき、多くの方が頭を悩ませるのが財産分与です。結婚生活を通じて築いた財産を公平に分けることは、離婚後の生活を安定させるためにも非常に重要です。しかし現実には、離婚の協議がうまく進まず、先に離婚だけが成立してしまうことも少なくありません。そのような場合、「もう財産分与は無理なのでは」と諦めてしまう方もいます。
実は、離婚後でも財産分与を請求できるケースも少なくなく、適切な手続きを踏めば権利を守ることができます。離婚後の財産分与は、離婚時に話し合いがまとまらなかった人や、財産の存在が後になってわかった人にとっても重要な手段です。
今回のコラムでは、離婚後でも財産分与を受けられる条件や手続き、注意点を詳しく解説します。
離婚後に財産分与は可能か?
多くの方は「離婚が成立したらもう財産分与はできないのでは」と考えがちですが、実際には離婚後でも請求は可能です。たとえば、離婚協議の際に財産分与について十分な話し合いができなかった場合や、離婚後に配偶者が財産の一部を隠していたことが判明した場合には、財産分与を請求することができます。重要なのは、「離婚が成立した時点で権利が消えるわけではない」ということを知っておくことです。
離婚の形によって手続き方法には違いがあります。協議離婚の場合は、まず当事者同士で話し合いを行います。話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停は裁判所が間に入り、中立的な立場で話をまとめてくれるため、感情的な対立があっても解決しやすい方法です。それでも合意に至らなければ、裁判で請求する道もあります。裁判では、財産の状況や夫婦間での貢献度を客観的に判断したうえで分与の割合が決まります。
ポイントまとめ
▪️離婚後でも財産分与は請求可能
▪️協議・調停・裁判いずれの方法も選択肢として存在
▪️財産の存在や分与について合意できなかった場合も請求可能
離婚後に財産分与を請求する際は、まず「自分にはどの財産に権利があるか」を整理することが大切です。この整理ができていないと、話し合いの場でも不利になりやすくなります。
財産分与の種類
財産分与にはいくつかの種類がありますが、離婚後に請求できるのは主に「清算的財産分与」です。これは、離婚時に夫婦が築いた財産を清算し、公平に分けることを目的としています。たとえば住宅や貯金、株式や自動車など、結婚生活の中で取得した財産が対象です。
一方、慰謝料は精神的な損害に対する賠償であり、本来、財産分与とは性質が異なります。離婚後に慰謝料請求を検討している場合でも、財産分与とは別に考えるのが基本です。また、婚姻期間中の厚生年金や共済年金については「年金分割」として分けられることがありますが、これは希望者のみが対象です。
財産分与は「結婚生活で共に築いた財産を公平に分ける行為」と覚えておくと分かりやすく、離婚後の生活設計を考える上でも大きな意味があります。
ポイントまとめ
▪️清算的財産分与が基本
▪️慰謝料とは目的が異なる
▪️年金分割は希望者のみ
たとえば、離婚時に住宅ローンの名義や残高、預金の額について話し合いがつかなかった場合、離婚後でも清算的財産分与を請求することにより、生活の安定を確保することが可能です。
財産分与の請求方法
離婚後に財産分与を請求する場合、まずは配偶者との話し合いから始めるのが基本です。話し合いで合意できれば、合意内容を書面にしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。しかし現実には、感情的なもつれや価値観の違いから話し合いがまとまらないことも少なくありません。その場合は、家庭裁判所の調停を利用します。調停では、裁判所が間に入り、中立的な立場で分与額や分配方法を整理してくれるため、感情的な対立を避けつつ解決を目指せます。さらに調停でも合意に至らなければ、裁判で請求することも可能です。裁判では、財産の状況や夫婦間の貢献度、生活状況などを総合的に考慮して分与の割合が決まります。
請求にあたっては、財産を証明する書類を揃えることが重要です。預金通帳や給与明細、不動産の登記簿など、財産の存在や範囲を示す証拠があると請求を有利に進めやすくなります。証拠が不足している場合、請求自体が難しくなることもあるため、離婚後すぐに整理しておくことをおすすめします。
ポイントまとめ
▪️まずは話し合いで請求
▪️協議で合意できない場合は調停・裁判
▪️証拠書類を揃えることが大切
財産分与を請求できる期間(消滅時効)
離婚後の財産分与には請求期限があります。原則として、離婚成立後2年以内に請求しなければなりません。これは法律で定められた「消滅時効」と呼ばれる期間で、期限を過ぎると財産分与請求権が消滅する可能性があります。期間内に請求できない場合は、早めに弁護士に相談して、適切な対応を検討することが重要です。
この2年という期間は、意外と短く感じる方も多いですが、請求に必要な書類の収集や財産の整理、調停・裁判の準備には時間がかかります。特に離婚後は、新しい生活の準備や仕事、子育てなどで手が回らなくなることもあるため、できるだけ早く行動することが権利を守る上で欠かせません。
ポイントまとめ
▪️財産分与請求は離婚後2年以内が原則
▪️期限を過ぎると請求権が消滅する可能性
▪️早めの相談で権利を守る
離婚後の財産分与で注意すべきポイント
離婚後の財産分与では、いくつか注意点があります。まず、配偶者が財産を隠したり、名義を変更したりするケースがあり、これがトラブルの原因となることがあります。たとえば、離婚前に共同で購入した不動産を離婚後に単独名義に変更する、あるいは預金を別口座に移すといった行為です。こうした場合でも、適切な手続きを踏めば請求は可能ですが、証拠の整理が不十分だと請求自体が難しくなることがあります。
また、財産分与をめぐる争いは長期化しやすく、精神的な負担も大きくなります。トラブルを避けるためには、財産の整理や証拠の確保、計画的な手続きが欠かせません。加えて、弁護士に相談することで、財産の範囲や分与方法を客観的に判断してもらえるため、安全かつ確実に手続きを進めることができます。
ポイントまとめ
▪️財産隠匿や名義変更に注意
▪️証拠を整理してトラブルを回避
▪️弁護士に相談することで安全に手続きを進められる
おわりに
離婚後でも財産分与は請求可能であり、請求期限や手続きの流れを理解しておくことが大切です。財産分与の請求は決して難しいものではありませんが、証拠の整理や適切な手続きが欠かせません。離婚後の財産分与に不安がある場合は、早めに弁護士に相談して権利を守る準備を進めることをおすすめします。
離婚は人生の大きな転換点です。経済的な面で不安を残さず、新しい生活を安心して始めるためにも、財産分与について正しい知識を持ち、必要な手続きを迅速に行うことが重要です。
当事務所では、離婚問題、財産分与について、数多くの問題を解決してきた実績があります。財産分与でお悩み・お困りの方は、初回無料にて相談を受けておりますので、お気軽にご相談ください。